市民の科学への不信はいかにして形成されるか(前半)
――「歪曲」されたリスク評価の事例の検討――
2010年11月30日
柳原敏夫
目次
(以下は->後半)
はじめに――問題の分類――
1、問題提起
一般にリスク評価とは、例えば米国産の牛肉を輸入した場合、狂牛病の危険があるかどうかが不確実であるとき、このような不確実な事態をどう評価し(認識の次元)、その評価を踏まえてどう対処するか(実践の次元)といった問題である。分かりやすく言えば、いかにしたら不確実な事態に適切に評価しそして適切に対処しうるかという問題である[1]。
ところで、この問題を一般的、抽象的に論じてみてもそれは「死んだリスク評価論」にしかならない。これを生きたリスク評価論にするためには、生きた事例の中から生きた教訓を汲み取る必要がある。本章は「生きた事例」として遺伝子組換え技術の具体的事例を取り上げ、その検討を通じてこれを試みるものである。
2、問題の整理
最初に、「危険かどうか不確実な事態」を2つに分類する。1つは、「不確実な事態」といっても、危険な事態の発生を科学的に予測することが可能なケースである(さしあたり、これを古典型リスク評価と呼ぶ)。もう1つは、「不確実な事態」を、その当時の科学水準に照らし、危険な事態の発生を科学的に予測することが不可能なケースである(さしあたり、これを現代型リスク評価と呼ぶ)。後者の実例は、米国産の牛肉を輸入することが狂牛病に関して危険かどうかを評価するような場合である。後者はいわば科学の限界の問題であり、そのため「危険かどうか不確実な事態」の科学的評価は困難を極める。これに対し、前者は科学の範囲内の問題である。一見ここには「不確実な事態」はないように見える。にもかかわらず、例えば危険な事態が発生したとしても、現実の被害が顕在化するまでは発生した事実を科学的に証明するのが困難なため、そのために「不確実な事態」であるかのように見えるケースである。
本章では前者(古典型リスク評価)のケースを取り上げる。後者(現代型リスク評価)のケースに比べ、これは科学の手で結論を出せるので、本来、いかに不確実な事態を適正な評価したらよいかという問題に悩む必要なぞないように見える。しかし、ここでは、というよりここでこそリスク評価に潜む最も核心的な問題が浮上する。それは、科学の名においてリスク評価が「歪曲」され、市民の科学への不信が形成される場面だからである。以下の遺伝子組換え技術の「生きた事例」はそれを明るみにしてくれるだろう。
第1部:古典的リスク評価の検討――事例検討――
1、遺伝子組換え技術
遺伝子組換え技術とは何か。例えばどうして北極海や南極海にすむ魚(カレイなど)は凍らないのだろうか?それは、魚が自分の体液を凍らせないタンパク質、つまり不凍タンパク質を作っているからだと分かった。そこで、これを応用できないかと考え、カレイの不凍タンパク質を作る遺伝子をカレイのDNAから取り出して、それを植物(トマトなど)のDNAに組み込む技術が開発された。これが遺伝子組換え技術である。これにより、もともとカレイが作っていた不凍タンパク質をトマト自身が作るようになれば寒冷地でもきっと冷害に強いトマトができるだろう、それが開発の理由である。このように特定の目的のために、特定の機能を果たすタンパク質を作り出す遺伝子を別の生物から取り出し、その遺伝子を目的の生物のDNAに組み込み、その遺伝子から必要なだけ(通常は「強力に」)目的のタンパク質を作るように改造する、この生命に対する操作のことを遺伝子組換え技術という。
2、遺伝子組換え技術は2度操作する
「遺伝子組換え技術は2度操作をする、一度目は生命に対して、二度目は世論(市民)に対して。」
もちろんこれは仮説である、このようなことはあってはならないという意味での。但し、遺伝子組換え技術の専門家は元々操作のプロということもあって、操作は身についた仕業なのかもしれない。そこで、このような仮説がなぜ、どのようにして唱えられることになったのか、次の遺伝子組換え技術の具体的な事例を通じて検証を行い、今後そのような嫌疑が二度と起きないようにするために何をしたらよいか考えてみたい。
3、遺伝子組換え技術の事例――GMイネの野外実験――
本章で取り上げる遺伝子組換え技術の事例(以下、本事例という)とは次のことをいう。
1998年、それは次のようなアイデアで始まった――カラシナという野菜が病気に強いのはカラシナが病原菌を殺菌するディフェンシンという抗菌タンパク質を作るからだと分かった。そこで、遺伝子組換え技術を用いて、このタンパク質を作り出すカラシナの遺伝子をカラシナから取り出しイネのDNAに組み込み、イネ自身が常時ディフェンシンを作り出すように生命操作できれば、きっと病気に強いイネができるにちがいない(下の図参照)。これこそ農薬を使わないでも丈夫なイネが育てられ、環境に優しく病気に強い夢のイネではないか。こうしたアイデアで始まった研究で作り出された遺伝子組換えイネ(以下、GMイネと略称)が屋内実験でイネを悩ます病気(いもち病や白葉枯れ病など)に強いことが証明されたとして、2005年春、実用化に向けて、新潟県上越市で屋外実験が日程にのぼった。
|
野外実験を実施した北陸研究センターのHPを参考に作成
|
4、悪夢から眺めた仮説
「遺伝子組換え技術は2度操作する」、今この仮説を、遺伝子組換え技術による悪夢=危険な事態(生物災害など)の発生という側面から眺めると、次のように言い換えることができる。
「遺伝子組換え技術による危険な事態(生物災害など)は2度発生をする、一度目は研究段階での生命操作において見込み違いや偶然の要素によって発生し、二度目は社会との交渉の段階での世論操作において確固たる必然の要素によって発生する。」
本事例で問題となった危険な事態とは生物災害である。具体的にそれは、本年(2010年)9月に抗生物質に対する多剤耐性菌(アシネトバクター・緑膿菌)により多数が死亡し大きな社会問題となったが、これより桁はずれの危険性を持つディフェンシン耐性菌の出現とその増殖・伝播という問題である。
5、古典的テーマ――耐性菌問題
耐性菌も含め、一般に耐性とは、同じ薬剤(抗生物質・殺虫剤・除草剤など)を使い続けると、やがてその薬剤が効かなくなる現象のことをいう。最初に発見された抗生物質であるペニシリンが実用された1941年から10年もしない1940年後半に黄色ぶどう球菌でペニシリンが効かなくなる耐性菌が出現した。1950年代にはその後発見された多くの抗生物質に対しても耐性菌が出現して、化学療法の成果を台無しにした[2]。殺虫剤をくり返し使用すると殺虫剤で死なない虫が繁殖しはじめるという事態が大きな社会問題になったのは1940年代後半だった[3]。除草剤について耐性雑草が最初に見いだされたのはアメリカで1970年のことである[4]。
つまり、本事例の研究がスタートした20世紀末において、耐性菌問題とは狂牛病などの現代的な生物災害とは異なり、科学研究の上ですでに古典的な生物災害であり、抗菌剤や抗菌タンパク質を開発する研究者なら誰もが避けて通れない普遍的な課題として認識されていた。
では、この古典的、普遍的なテーマについて、本事例の研究者たちは具体的にどのように取り組んでいたのだろうか。
6、仮説の検証(1度目の操作:研究段階
本事例の研究者たちは、野外実験を実施する直前に発表された論文(以下、本論文という)の中で、古典的、普遍的なテーマである耐性菌問題について、次のように述べていた。
「作物の病害抵抗性育種を目指す際に常に問題となる大きな問題の一つとして、病原菌の変異による抵抗性崩壊(ブレイクダウン)[5]があげられる。イネ育種の場合でも、特に真性抵抗性遺伝子[6]をもつ系統・品種は、しばしばこの問題に直面することが知られている。ディフェンシン遺伝子を導入した組換えイネもまた、抵抗性崩壊をひき起こすのだろうか。抗生物質などと比較して、抗菌蛋白質は一般的に病原菌に対して“穏やか”に作用すると考えられている。また、抗菌蛋白質が細胞膜に作用するという特性上、病原菌が細胞膜の構造を劇的に変化させることで抗菌蛋白質の攻撃を“解決”するにはあまりに大きな遺伝的変化を必要とするため(1)、抗生物質や農薬の主成分である薬剤と比較して、抗菌蛋白質では抵抗性崩壊の懸念は低いと考えられている。筆者らは現在、ディフェンシン、抗生物質および農薬の有効成分を用いて耐性菌の出現頻度の比較解析研究を進めている。‥‥
文献
(1) M. Zasloff :Nature, 415,
389 ( 2002)」(雑誌「化学と生物」2005年NO4掲載の論文「抗菌蛋白質ディフェンシンの多様な機能特性」233頁左21行目以下)
つまり、研究者同士の発表の場では、彼らは次の認識を表明していた。
①.本事例のように、作物の病害抵抗性育種を目指す際に常に問題となる大きな問題の一つとして「耐性菌問題」があること。
②.耐性菌が出現するかどうかについては、抗生物質による耐性菌と対比して考察するという方法を取ったこと。
③.その結果、抗生物質とを比較し、本事例のような抗菌タンパク質は一般的に病原菌に対して“穏やか”に作用すると考えられていること、抗菌タンパク質研究の権威とされるZasloff博士の仮説に依拠して、抗菌タンパク質が細胞膜に作用するという特性上、病原菌が細胞膜の構造を劇的に変化させることで抗菌タンパク質の攻撃を“解決”するにはあまりに大きな遺伝的変化を必要とすること、以上から、抗生物質と対比し、抗菌タンパク質では耐性菌の出現の頻度は低いと考えられること。
④.現在、本事例の抗菌タンパク質であるディフェンシン、抗生物質および農薬の有効成分を用いて耐性菌の出現頻度の比較解析研究を進めている。
この論文の記述を信用する限り、彼らは、夢の開発というコインの裏側の悪夢について、科学者の常識に従って、耐性菌問題のリスク評価と対応を実施している。すなわち、
(1)、本事例で、常に問題となる大きな問題の一つとして「耐性菌問題」が存在することを明言し、
(2)、耐性菌出現の可能性の評価方法として、過去に豊富な耐性菌問題を経験済みの抗生物質の場合と対比して考察するという方法を採用し、
(3)、その上で、Zasloff博士の仮説に依拠して、さしあたり耐性菌は出現するだろうが、しかしその頻度は「低い」と評価し、
(4)、今後の対応として、この仮説による暫定的な評価で間違っていないか、引き続き、抗生物質および農薬による耐性菌のケースと対比して、耐性菌の出現頻度を比較解析することにした。
この当時、抗菌タンパク質による耐性菌の出現の可能性について、2つの仮説、つまり、一方は抗生物質とは異なり、「極めて考えにくい(surprisingly improbable)」とする2002年のZasloff博士に代表される仮説と、他方はこれに反対し、抗生物質と同様、耐性菌は容易に出現するという仮説[7]とが並び立っていたのだから、本事例の研究者たちは、抗菌タンパク質研究の権威とされるZasloff博士の見解にさしあたり依拠するとしても、それが間違いである可能性もある以上(実際、彼らの論文発表後半年余りで、Zasloff博士の仮説の誤りが実証された[8])、引き続き、その仮説の検証作業を行うという対応をしたのである。これなら、仮に彼らの見込み違いにより耐性菌が出現したとしても、それはいわゆる拡散防止措置が施されている実験室内のことであり、通常であれば社会問題にはならずに済む。また、仮説の検証作業の中で、彼らの見込み違いが判明して、社会問題になる前に適切な軌道修正が可能となる。
以上の通り、研究者同士の発表の場で発信した言説(本論文)でみる限り、彼らは研究段階において、耐性菌問題のリスク評価として至当な振る舞いをしたと評することができる。
ところが、そのあと突然、不可解な振る舞いが生じた。
7、仮説の検証(2度目の操作その1:国の事前審査の段階)――消えた耐性菌問題――
耐性菌出現の可能性について、本事例の研究者たちは、本論文で、出現の頻度は「低い」とするZasloff博士の仮説に依拠することにし、なおかつその仮説の検証を継続するという対応をしていると述べたが、本論文が発表される約半年前に、彼ら(正確には彼らが所属する研究機関、法的には独立行政法人)はGMイネの野外実験を実施するため、国に承認を得るための申請書を提出した(2004年11月17日第一種使用規程承認申請書)。
つまり、彼らの研究が密閉され拡散防止措置が施されている屋内実験の段階から開放され拡散防止措置が施されない屋外実験に移行する場合には、自然環境と大きな関わりを持つことになるので、実験の安全性が社会的な問題としてクローズアップされ、国による事前の承認が必要になる。
とはいえ、野外実験の内容自体、基本的にそれまでの屋内実験の延長である。だとしたら、屋内実験で明らかにされた安全性をめぐる諸問題が引き続き野外実験においても吟味検討されることになる(むろん、それまでの屋内実験では問題にならなかった、自然界の植物との花粉の交雑といった野外実験に固有の問題も新たに登場する)。
従って、本来ならば、承認申請書の提出にあたって、本事例の研究者たちが本論文で明らかにしたように、《作物の病害抵抗性育種を目指す際に常に問題となる大きな問題の一つとして》「耐性菌問題」があることが、本承認申請の中心的テーマとして真っ先に取り上げられる筈であった。
しかし、現実の承認申請書には耐性菌のたの字もなかったのである。この不可解な出来事は何故起きたのだろうか。つい最近まで《作物の病害抵抗性育種を目指す際に常に問題となる大きな問題の一つとして》「耐性菌問題」を取り上げ、《現在、ディフェンシン、抗生物質および農薬の有効成分を用いて耐性菌の出現頻度の比較解析研究を進めている》と言明した彼らがつい誤って書き忘れたということはあり得ない。すると残された可能性は、意図的に「耐性菌問題」を記載しなかったということである。つまり、純然たる研究段階から社会的な接点が始まる野外実験の承認申請段階に移行した時点で、「耐性菌問題」は突如消されたのである。
この点について、真摯な研究者なら次のように考えるだろう――科学研究では予測不可能な現象は常にある。その場合、本事例の研究者が本論文で発表したように、暫定的な立場をひとまず仮定して、なおかつその仮説の検証を続行するのが研究の常道である。仮説の検証の中で、或る程度成果が得られたら、その成果に基づいてより確固たる立場に立つことができるだろう。野外実験の承認申請書にも、こうした仮説の検証の成果とそれに基づいた彼らの見解を披露して、実験の安全性を堂々と主張すればよい。それがまともな研究のやり方だ、と。
しかし、本事例の研究者たちもその研究機関もそれをしなかった。研究者同士の発表の場(いわば研究者にとって内部の世界)では、「常に問題となる大きな問題の一つ」である「耐性菌問題」について、まっとうなリスク評価とそれに基づく対応を取ることを表明しながら、ひとたび市民生活や自然環境といった社会的な問題が問われる場面(いわば研究者にとって外部の世界)になると、そもそも「耐性菌問題」など存在しないと言わんばかりの、手の平を返したような正反対の態度を取るに至ったのである。こうして、彼らやその研究機関は科学者として自身が所属する内向きの顔と社会や市民に対する外向けの顔とを使い分けるに至ったのである。
ここから何が導かれるだろうか。何よりもまず、野外実験では、耐性菌が出現した可能性が高いと推論できることである。なぜなら、本事例の研究者たちは、《現在、ディフェンシン、抗生物質および農薬の有効成分を用いて耐性菌の出現頻度の比較解析研究を進めてい》て、その研究成果がもし彼らの依拠するZasloff博士の仮説通りもの、つまり「耐性菌の出現の頻度は低い」のであれば、単にこれを野外実験の承認申請書に堂々と記載すれば済むだけのことだからである。それを敢えてしなかったのは、彼らの比較解析研究がまっとうな研究であったため、その研究成果が、その後話題となった著名な実験結果[9]と同様、Zasloff博士の仮説を否定するもの(つまり、ディフェンシンにより耐性菌が容易に出現する)だったからである。つまり、この段階で、彼らは本論文に記載した自分たちの見込みが間違っていたと気がつくに至った筈である。
こうして、本事例の野外実験で、耐性菌が出現した可能性が高い。本論文執筆当時の研究段階では、仮に見込み違いにより耐性菌が出現したとしても、拡散防止措置が施されている屋内実験であるためそれによる被害は取り立てて問題にするまでもなかった。しかし、ひとたび屋内実験から野外実験に移行した場合は状況が一変する。野外実験で耐性菌出現が実験場外の環境にもたらす影響については、計り知れないものがあるからである。
しかも、前述の通り、《ディフェンシン、抗生物質および農薬の有効成分を用いて耐性菌の出現頻度の比較解析研究を進め》た本事例の研究者たちは、野外実験の承認申請の段階で彼らの見込みちがいに気がついていたと思われる。にもかかわらず、承認申請の準備の中で最終的に、彼らとその研究機関は「耐性菌問題」を消去した。なぜリスク評価にとって古典的、普遍的な重要論点を消去するような不可解な真似をしたのだろうか。考えられることは、もしも承認申請書に何かしら「耐性菌問題」について記述した場合には、必ずその対策について問い質され、質疑応答の末、「耐性菌問題」の対応が不十分として野外実験が却下されることを恐れたからであり、これ以外の合理的な理由は考えられない。
尤も、真摯な研究者なら、そこで次のように考えるだろう――たとえ野外実験の承認申請書に「耐性菌問題」を書き落としたとしても、申請書の審査の中で、必ず「耐性菌問題」はどうなのか?と質問されるにちがいない。そして、その対策をどうするのか追及される。なぜなら、本事例のように、病害に強い育種を開発する場合、「耐性菌問題」は「常に問題となる大きな問題の一つ」であることは専門家にとって古典的な常識なのだから。
ところが、ここで奇跡が起きた。本事例ではそのような質問は起きなかったからである。むろん審査を行なう場(総合検討会)には微生物の専門家はいた。にもかかわらず、検討会の委員から誰一人、「耐性菌問題」について質問は出なかった。そのため、真摯な研究者が予期した「耐性菌問題」に対する追及もなかった。このときの総合検討会の微生物の専門家の発言は次のようなものだった。
≪日本初といいますか、有用な遺伝子がこういう形で使われるというのは非常にいいことで、うれしいことだと思うんです[10]≫
かくして、本事例の野外実験は国の事前審査におけるリスク評価をめでたくパスしたのである。
ちなみに、この発言をした微生物専門家はのちに、本事例が市民により野外実験中止の裁判(以下、本GMイネ裁判という)が起こされると、本来中立の立場である筈の審査会の委員の立場を忘れ、裁判の被告=本GMイネの開発側が主張する重要な主張を裏付ける書面の作成者として幾度も登場し、多大な貢献をした。その結果、本GMイネ裁判に関わり、国の事前審査と裁判の経緯を一部始終目の当たりにした市民の胸中には、科学と科学者に対する回復し難い不信感が形成されたのである。
以上が本事例の野外実験の事前審査の段階におけるリスク評価の実情である。
8、仮説の検証(2度目の操作その2:裁判手続きの段階)――耐性菌問題の創作物語――
ところが、本事例の野外実験は国の事前審査段階はなんなくパスしたものの、そのあと、おもいがけない事態に発展した――多くの地元市民から野外実験中止を要請する声があがり、その際、研究機関側の対応がすこぶる不誠実であるとして、とうとう市民から野外実験中止の裁判を起こされてしまい、裁判手続の場で、再び「耐性菌問題」をめぐるリスク評価が問われることになったからである。
もともと裁判は人生のリトマス試験紙である。裁判というるつぼにほおり込まれたすべて人たち(むろん裁判官も例外ではない)の正体を否応なしに、情け容赦なく無慈悲に暴き出す。
例えば、野外実験で市民からの異議申立を全く予想していなかった被告=本事例の研究者たちとその研究機関はうろたえてしまった。そこで、裁判の最初の書面(答弁書)で次のように締めくくったのである。
≪いずれにせよ、本申立は、本実験を批判し、批判を喧伝する手段の一つとして行われたとしか考えられず、手続を維持するだけの法律上の根拠は全く認めることができない。いずれにせよ、本申立においては、そもそも一般的な高等教育機関で教授ないし研究されている遺伝子科学の理論に基づいた主張を展開しているものではなく、遺伝子科学に関し聞きかじりをした程度の知識を前提に特定の指向をもった偏頗な主張を抽象的に述べているに過ぎず、また法的に考察しても非法律的な主観的不安を書きつらねただけのものとしか評価しようがなく、債務者としてはかような仮処分が申し立てられたこと自体に困惑するばかりである。
本申立について、一刻も早く却下決定を賜り、債務者を本手続から解放いただきたい。≫(2005年6月28日債務者(注:被告のこと)の答弁書19頁)
このとき、本事例の研究者とその研究機関の前には2つの選択肢があった、ひとつは、本論文で表明したような、科学者の間で常識とされる「耐性菌問題と真摯に取り組む」立場を表明するやり方、もうひとつは、これとは正反対の、野外実験の承認申請書に示したような「本事例にはそもそも耐性菌問題は存在しない」という立場を取り続けるやり方である。しかし、彼らは、当初、科学者としての良心と国策(バイオテクノロジーの推進)とのはざ間で悩んでいたのか、考えを整理できなかったようである。そのため、さきほどの答弁書では、次の通り、この2つの選択肢を折衷した支離滅裂な主張になってしまった。
≪ディフェンシン蛋白質のような抗菌性タンパク質の場合、抗菌作用は穏やかであり、耐性菌の出現の余地は科学的になく、また実際耐性菌の出現についての報告もない。≫(答弁書12頁)
つまり、「抗菌作用は穏やかであり」は本論文の記述通りである。にもかかわらず、ここから本論文の帰結である耐性菌の出現の「懸念は低い」というグレーゾーン的な結論に行かず、「耐性菌の出現の余地は科学的になく」という完全なシロ、すなわち野外実験の承認申請書の立場に無理やりつなげてしまったからである。
しかし、この答弁書に対し、原告市民に協力的な研究者から、本論文中に引用されていた耐性菌出現を報告する論文から野外実験においてもディフェンシン耐性菌が出現する可能性は高いと推測することが合理的であると指摘されると、被告=本事例の研究者たちは次のように反論した。
《極めて特異な人工的環境での人為的耐性菌作出の事実を以て「自然界でのディフェンシン耐性菌出現が報告された」と誇張するなど》《極めて特異な人工的環境での人為的耐性菌作出の事実を以て、自然界における他の生物相等の環境影響が存在することを捨象し、科学的メカニズムの解明なしに、自然界でのディフェンシン耐性菌出現に飛躍している》(いずれも平成17年8月12日被告準備書面(4)5頁)
つまり、耐性菌が実験室で発生したからといって自然界でも発生すると推定することはできないという反論である。これに対し、再び原告市民に協力的な研究者から、実験室で発生した結果から自然界でも発生すると推定することは十分合理的であることを詳細に証明する反論書が提出された。これを受けて、本事例の研究者たちは、実験室の結果と自然界の結果は無関係であるという反論はもはや維持できないことを悟り、「耐性菌の出現の余地は科学的にない」ことを導く新たなロジックを見つけ出すしかないと奔走し、その結果、遂にこれを発見した――それが、①GMイネが作り出すディフェンシンはイネ体内の細胞壁と強固な電気的に結合するので、いったん細胞壁と結合したら離れない。→②その結果、ディフェンシンがイネ外部に溶出することは不可能→③その結果、ディフェンシン耐性菌の出現は不可能→④従って、本事例の耐性菌問題が存在しない、というロジックだった。これにより耐性菌は「発生可能性がないことが科学的に公知」(平成17年9月27日被告準備書面(5)9頁第6、2)な事実とされたのである。
このとき、本事例の研究者たちは前記の2つの選択肢のうち後者の立場、すなわち野外実験のスムーズな承認を得るために承認申請書の作成に際しておこなった最初の世論操作である「本事例にはそもそも耐性菌問題は存在しない」という立場に完全に立つ決断をした。しかも、承認申請書では、「沈黙」という消極的なやり方であったのに対し、裁判ではもはやそのような「沈黙」は許されず、自ら積極的に、なにゆえ「本事例にはそもそも耐性菌問題は存在しない」のか、そのからくり(メカニズム)を積極的に説明することを迫られ、その結果、科学上の新発見ともいうべき「ディフェンシンはイネの細胞壁といったん結合したら離れない」という見解を論拠に、そこからそもそも耐性菌は出現の余地がないという結論を導き出すことになったのである。しかし、学界ではこれまで、本事例の研究者を含め誰ひとり、そのようなメカニズムを発表した者はおらず、それはさながら「耐性菌問題」をめぐる前代未聞の創作物語の誕生であった。
なぜなら、もしそのメカニズムが真に科学的な裏付けを持つのであれば、彼らが主張した「ディフェンシンはイネの細胞壁といったん結合したら離れない」という新事実を、少なくとも、誰がいつ、どのようにして発見をしたのか、その論拠を示す筈であるが、彼らは一切示さなかった。また、もし自ら実験で実証したというのであれば、その実験結果は、何よりもまず耐性菌の出現で悩み続けてきた彼ら自身の福音である。まっさきに、それを論文として発表し、ディフェンシンに関する本事例では耐性菌問題は存在しないから、心置きなく開発に専念できると公表する筈である。しかし、不思議なことに彼らは、本論文でもそのことを一言も言及しなかったし、それ以降もこれに言及した論文を一度も発表しなかった。では、なぜ発表しなかったのだろうか。それは、とても研究者同士の場で発表できるような内容ではなかったからである。だから、ひたすら研究者の外部の世界に向けてだけこれを言い続け、研究者の内部の世界ではもっぱら沈黙に励んだのである。その結果、、研究者の内部の世界とその外部の裁判や市民生活といった社会関係の場で2つの正反対の見解、つまり一方では科学、他方では科学とは無縁のいわば偽科学またはジャンク科学が公然と語られるに至った。
9、世論操作の動機(最大の評価ミス:ディフェンシン耐性菌の危険性について)
では、なぜ本事例の研究者たちは、承認申請書の作成にあたって、「耐性菌問題」を消去したのだろうか。むろんそれによって野外実験の承認が却下されることを免れるためだったにちがいない。
ただ、ここで問題にしたいことはそのことではなく、なにが彼らの世論操作を支えたのか、言い換えれば世論操作を正当化させたのか、である。しかも、彼らの認識の次元でそれについて考えてみたい。
前にも述べた通り、裁判はリトマス試験紙である。裁判に関係する者は否応なしにその正体をさらけ出す。それは咄嗟の瞬間において一層顕著である。被告=本事例の研究者たちも、予期していなかった裁判を地元市民から起こされたとき、「耐性菌問題」に対して、最初の答弁書で、彼らを次のように本音を明かした。
≪万が一ディフェンシン耐性の菌が出現したとしても、現行農薬に対する耐性菌ではないため、現行農薬で十分対処できる≫(12頁12(2))
つまり、仮に「耐性菌問題」が発生しても、現行農薬で殺菌すれば対策は十分だ、と。この当時、被告=本事例の研究者たちの認識は、本件の「耐性菌問題」とはあくまでもイネの問題であって、それ以上でもそれ以下でもないと考えていた。つまり、イネの問題は≪現行農薬に対する耐性菌ではないため、現行農薬で十分対処できる≫、だから、「耐性菌問題」を恐れる必要はない、だから、これを承認申請書から消去してもたいした問題でもない、と。「本件の耐性菌問題=イネ問題」という事実認識、これに支えられて、彼らは承認申請書で「耐性菌問題」の消去に踏み切ったものと思われる。
しかし、この事実認識は完全な誤りである。のみならずこの事実誤認こそ本研究プロジェクト最大の失態である。なぜなら、本件の「耐性菌問題」が発生したら、その現実の被害はイネにとどまらず、人間も含めて、およそ地球上のディフェンシン[11]を産生する全ての動植物、昆虫たちの生体防御に被害を及ぼす可能性があるからである。従って、最悪の場合には、人の健康被害、地球上の生態系の破壊という人類と地球環境に深刻な被害をもたらす。その可能性は微生物学者にとって常識である。この点、微生物生態を専攻する東京大学大気海洋研究所の木暮一啓教授は次の通り指摘した。
≪注意しなければいけないのは、ディフェンシンなどの抗菌タンパク質への耐性菌が抗生物質耐性菌よりもはるかに危険度が高い菌だという点です。抗生物質は微生物が生産する抗菌物質であり、ヒトの病気治療に使うものであって、抗生物質耐性菌は、あくまでも感染症にかかった人や外科手術を受けた人など抗生物質を使用する必要がある人にとっての問題です。
これに対し、ディフェンシンなどの抗菌タンパク質は、動植物が病原菌から身を守るための最初のバリアとして作るものであり、抗菌タンパク質への耐性菌は、そのバリアを打ち崩すもので、いわば病原菌に対する動植物の重要な武器を無効にしてしまうものです。したがって、健康に生活している我々ヒトのみならず動植物全般が、今までの自然の防御機構で対処できなくて、わずかの菌の攻撃にも耐え切れずに感染・発病してしまうという大問題を起こします。だから、大変危険なのです。そのことが最近になって次第に世界的に認識されてきて、昨年末には世界的に有名な科学誌であるNatureにも、抗菌タンパク質の濫用を戒める論文が出ています(甲21。Nature 2005年11月10日号)。≫(2006年7月11日意見書(2)[12]6頁)
しかし、本事例の研究者たちは誰ひとりこの重大な事実に気がつかなかった。皆、本件の「耐性菌問題」を抗生物質や農薬の使用による耐性菌の問題と同様に考えれば足りると、すなわち、耐性菌の「出現」の可能性について、抗生物質や農薬の場合と対比して考えればよいのと同様、出現した耐性菌の「危険性」についても、やっぱり抗生物質や農薬の場合と対比して考えればよいと思い込んでしまった。
その思い込みの最大の原因は本事例の研究者たちがもっぱら病気に強いイネの開発しか頭になかったことにある。その結果、彼らが参照した抗生物質や農薬の使用による耐性菌問題ではそれらを使用する入院患者や野菜のことだけ考えればよかったのだから、ディフェンシン耐性菌も同様に考えれば足りる、つまりイネのことだけ考えれば足りると思い込んでいたふしがある。つまり、彼らの研究体制として、イネの立場には立てても、菌(病原菌)の立場に立って現実を眺める専門家が誰ひとりいなかった。その結果、ディフェンシン耐性菌の危険性の程度(重大さ)を正しく認識できず、≪耐性菌なら農薬で対応万全≫と安易な気持ちで、野外実験のスムーズな承認のために「耐性菌問題の消去」に踏み切ってしまったのである。もしそのような事実誤認をしていなかったなら、つまりディフェンシン耐性菌は人類と地球環境に深刻な被害をもたらす可能性があるとその「危険性」を正しく認識していたならば、本件の「耐性菌問題」を消去するという大それた真似は≪早急に実用化を図る必要がある≫(野外実験の栽培実験計画書)と考えていた彼らもさすがに出来なかった筈である。第一、本GMイネ裁判で「耐性菌問題」を追及されたとき、答弁書に≪万が一ディフェンシン耐性の菌が出現したとしても‥‥現行農薬で十分対処できる≫という恥ずかしい答弁はしない。
10、二度目の操作の防止
前述した仮説をもう一度くり返す「遺伝子組換え技術は2度操作をする、一度目は生命に対して、二度目は世論(市民)に対して。」
生命に対する一度目の操作で認識上の誤りは避けられないが、しかし、世論(市民)に対する二度目の操作はそれ自体本来あってはならない。にもかかわらず、前記の事例が示した通り、その誘惑は強烈である。そして、それがもたらすかもしれない災害は甚大である。我々がこの誘惑を克服できないとき、我々の未来は取り返しのつかないものになるおそれがある。では、どうしたらその誘惑を断ち切ることができるだろうか。
前述した通り、ここには①意図したリスク評価の創作(法律の世界では「ねつ造」と言う)の問題と、②意図せざるリスク評価のミスの問題という次元が異なる2つの問題がある。
前者の問題を解決する原理は単純である――ウソをつくな。あとはこれを現実に担保する具体的な方策の問題だけである。しかし、現在のチェックシステムは一言で言って、ウソと茶番が容易に可能な馴れ合いのシステムである。少なくとも現在の検察審査会並みに、ウソと茶番を断ち切る抜本的な制度改革が不可欠であるが、ここではこれ以上立ち入らない。
以下、後者の問題、意図せざるリスク評価のミスの克服について述べる。前述した通り、本事例の研究者たちは野外実験のリスク評価を間違えてしまった――桁はずれの危険性を持った野外実験を地元住民の猛反対を押し切ってまでも強行することができた最大の理由は、彼らが野外実験により発生する「耐性菌問題」の危険性の程度を完全に見誤って、本GMイネの問題でしかないと信じ切っていたことによる。もし彼らが、ディフェンシン耐性菌問題の危険性を前記の通り正しく認識していたならば、とてもそのような暴挙を敢えて冒すことはできなかった筈である。
くり返すと、このような暴挙を可能にしたのはディフェンシン耐性菌の危険性に対する本事例の研究者たちのリスク評価のミスである。その際重要なことはこのミスが決して偶然のミスではなく、起こるべくして起きた必然だということである。なぜなら、効率的に技術開発を推し進める現代の工学の発想からすれば、本事例の研究者たちこそこの発想に最も忠実に、開発の目的であるイネに焦点を絞り、イネを中心にした各専門分野の研究者が集められ、そこに病原菌の専門家がいたとしてもそれはイネにとっての病原菌の専門家ではあっても、イネ以外の様々な動植物、昆虫の生き物にとっての病原菌についての専門家ではなかった筈である。しかし、自然界は別にイネの世界だけ細分化され、独立して存在している訳ではない。イネとイネ以外の様々な動植物、昆虫、微生物の生き物とは無数の相互関係の網目の中でつながっている。そのため、自然の一部分を変えようとすると、必ずほかに影響を与えないでいない。だから、イネ中心の知見しか持ち合わせていない専門家たちに、イネ以外の生物に与える影響を考察できないのは当然である。本事例の研究者たちがディフェンシン耐性菌がイネ以外の生物に与える影響を正しく評価できなかったのは必然である。そうである限り、今後もまた同様の過ちをくり返すのも必至である。
しかし、人は彼らのこのミスを笑うことはできない。ここには現代の「科学技術」が直面している構造的な原因に由来する普遍的な問題が横たわっているからである。つまり、成果をあげるために自然界を専門領域に細分化・分断するという方法で行く限り、現代の科学者・技術者なら誰もが同じようなミスをおかすおそれがあるのだ。
現代ほど「科学技術」の恩恵を受けた時代はない。次から次へと新たな「科学技術」が生まれ、「いつでも、どこでも、あらゆる『科学技術』の恩恵が利用できる環境」にある。しかし、それは同時にブラックボックスの時代である。我々市民は「科学技術」の恩恵をブラックボックスとして、いったいそれがどんな仕組みになっているのか全く無知のまま受け取らざるを得ない。その結果、次から次へと生まれた「科学技術」の成果から、衣食住の生活全般にわたって、かつてなかったような災害・被害にも見舞われることとなった。「いつでも、どこでも、あらゆる『科学技術』の災害・被害に見舞われる環境」となった(シックハウス、電磁波被害、食品添加物、化学物質過敏症、アトピーなど)。
しかも、深刻な問題はそれらの技術を開発した研究者たち当人にとってもその災害・被害がブラックボックスだということである。今日の「科学技術」はかつてないほど専門化、細分化、分断化していて、研究者は自分の専門分野に関し最先端の豊富な知見を持っているとしても、ひとたび専門以外の領域のことになると素人同然が珍しくなく、ブラックボックスの世界だからである。
だから、本事例の研究者たちが今回、ディフェンシン耐性菌の危険性をイネとの関係でしか考えられず、リスク評価を完全に見誤ってしまい、その結果、桁違いの危険な野外実験に踏み出してしまったことは、今日の「科学技術」の研究方法に従い開発している全ての科学者・技術者にとって肝に命じるべき訓えである。
今日ほど、「科学技術」の安全、安心が叫ばれる時代はない。しかし、それが口先ではなく、真に実効性あるものを目指すのであれば、前記のブラックボックスの問題を本当に克服する必要がある。
くり返すと、人がリスク評価を間違えるのは「不確実な事態」に直面したからではない。自然界を自分の都合で分割し、細分化してしまったため、そこからしか自然界を眺めることができなくなった必然の結果にほかならない。すなわち、現代「科学技術」の方法論そのものに原因がある。
従って、このようなリスク評価のミスを防止するためには、専門化、細分化、分断化している現代「科学技術」のシステムそのものを変革するしかない。
では、具体的にどうしたらよいか。ここからはアイデアと知恵の勝負である。現実の市民は生産の場では労働者であるが、他方、消費の場では消費者である。いま、消費者としての市民に着目したアイデアとして、
≪市民=労働者=消費者の手に<X>を取り戻す≫
というものがある。例えば、このXに、コンピュータの頭脳部分である「OS」を入れれば、昼間、企業でプログラマーとして働く労働者は、勤務外の場で自由となったとき、自発的に能力を発揮し、
≪市民=労働者=消費者の手にOSを取り戻す≫
つまり、巨大企業マイクロソフトを脅かす存在にまでなっているLinuxという無料OSを作り出す。
そこで、このXに、「総合化され、循環・連続を確保した科学技術」を入れれば、
≪市民=労働者=消費者の手に統合化、総合化され、循環・連続を確保した科学技術を取り戻す≫
となる。つまり、今日、様々な専門分野で科学者・技術者を職業とする多くの市民がいて、生産の場で効率的な開発に向けて前述の「科学技術」の方法で研究開発に従事している。しかし、ひとたび、彼らも勤務外の場で自由となったとき、それぞれの専門分野の立場から、本事例のような新しい研究開発に関する安全性について、自発的に発言を表明することができる。尤も、今日、科学者・技術者の勤務外での自由な発言も決して保障されていない。発言の結果、生産の場で有形無形の抑圧が加えられるからである。そのため、現実に「科学者・技術者の勤務外での自由な発言を保障」するための工夫が不可欠となる。例えば選挙における自由な投票を保障するための「秘密投票」のようなアイデアがここでも導入される必要がある。
他方、今日ほど科学技術と国家・企業との関係が深まった時代はなく、そのため、適正な技術評価を担保するためには、科学者・技術者の勤務外での自由な発言の場の運営を、漫然と国家・企業の手に任せるわけにはいかない。その結果、国家や企業から自立した市民組織(例えば国際技術評価センターなど)の手に運営を委ねる必要がある。この組織は市民の手で結成され運営される、科学技術評価に貢献する一種の消費協同組合である。
「ローマは一日にしてならず」。だが、このような科学技術評価に関する市民の消費協同組合が、最初は原子力発電、遺伝子組換え技術、食品添加物、化学物質過敏症といった具合に各分野ごとに作られ、のちにそれらが統合されて、全ての科学技術の評価について、日本のみならず世界中の「科学者・技術者の勤務外での自由な発言」を確保する場として機能するようになったとき、それは既成の国家の評価機関に替わり得る市民自身による評価機関として機能するだろう。それが、市民の、市民による、市民のための評価機関の第一歩である。
(第1部)
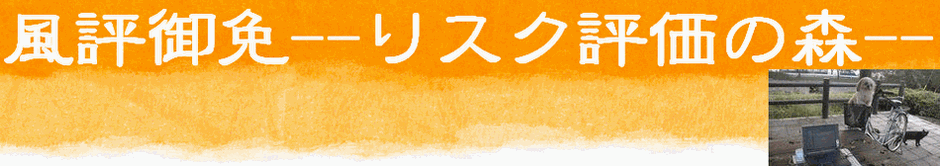

0 件のコメント:
コメントを投稿